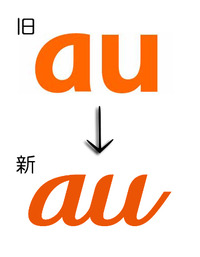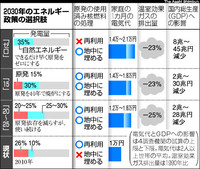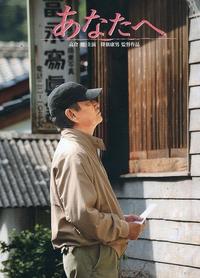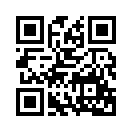2012年01月16日
検証、南西航空復活論:1

先日の記事 「南西空港」 で石垣市議会議員の砥板くんのブログで紹介されていた樋口耕太郎氏の南西空港復活に関するレポートが面白いと書いた。
ただその時点で、そのレポートの信憑性と実現性については僕なりに精査していなかったので評価することは避けた。
で、昨日は時間があったので検証してみた。
それを一度で書くと例のように長くなってしまうので(ただでさえ文章が長すぎるとこのブログを読んでいる友だちからは怒られています^^ゞ)、『検証:南西空港復活論』と題して何度かに分けて書いてみたい。
今日はその一回目、第1章:沖縄振興予算の問題点 →
検証:南西空港復活論
第1章:沖縄振興予算の問題点
「沖縄経済の牽引役は観光産業である」と一口に言っても、県民生活の端々を見渡すとき沖縄経済は国からの沖縄振興予算なしに成り立たないというのが実態である。
沖縄復帰以後これまで総額8兆円もの振興予算がつぎ込まれた。
基地負担の問題や振興予算投下に係るタイミング論※(1)はあるにしても、県外の政治家全般、国家官僚のほとんど、県民以外の国民の多くは、口には出さないが「沖縄にどれだけお金をあげればいいんだ?これまで8兆円もあげたんだからもう十分だろう!これ以上はいい加減にしてくれないか!」みたいな感情をいだいているのではないだろうか!?
しかも、樋口氏が指摘するように、長引く構造不況、東日本大震災に端を発する復旧復興予算の確保、原発の補償問題、電力不足、それによる産業の停滞に起因する「日本にお金がない」という状況…
この現実を前にするとき、いくら日本国には沖縄に対する責任があると言えども、日本が「ない袖は振れない」状況にあるなら、我ら沖縄は単に「自立経済」を標榜するのではなく、本気で自立しなければならない。
それを考える上で沖縄振興予算の問題点を指摘しておく。
沖縄振興予算の問題点、と言うとき、「沖縄自立経済の確立」の名のもとに膨大な予算がつぎ込まれ、それは結果的にそのスローガンとは逆の「補助金漬け」という依存型経済社会を醸成してしまった、という事態が想起されるが、それについては「沖縄振興予算の病理」というフレームで認識しておいていただきたい。
ここで言う問題点とは、必要なところに、必要な金額が、必要なタイミングで、使われてこなかったということ、特に必要なところとは何かということに日本も沖縄も真剣に考えてこなかったということとする。
沖縄復帰当時、高度経済成長真っ盛りの日本にはお金があった…本来は沖縄振興、沖縄自立経済確立のために綿密なグランドデザインを描き、それをひとつひとつ実行すべきだった。
お金のあった日本はそれをぜず、権力と利権構造の枠組みの中で沖縄の言われるがままに沖縄振興という名目で予算を付けてきた。
しかし、総額8兆円もの振興予算がつぎ込みながら沖縄経済はいまだなお自立を果たせていないという状況…
くりかえすが、経済の自立発展のための要諦は、必要なところに、必要な予算を、必要なタイミングで、使うことである。
今で言うなら、選択と集中、現代史の用語に当てはめるなら「傾斜生産方式※(2)」であり、そこには選択すべき、傾斜生産すべき、対象の「比較優位性と必然性」がなければならないということである。
平成15年?名護市にできたオフショア※(3)の沖縄金融センターを例にとって話してみよう。
この計画自体の発想は悪くない…と思う。
日本政府が沖縄振興の一環で、都市圏と同等のブロードバンド環境を整備した。
この環境を一つの必要条件として、オフショアの国際金融市場を名護につくることを日本政府に認めさせ実現したものだが、僕の評価としてはうまくいっているとは言えない。
というのも、名護に国際金融市場をつくる比較優位性に乏しく、必然性を見いだせないからだ。
比較優位性や必然性を考える場合、必要条件と十分条件ががともに存在することが最も重要である。
沖縄に国際金融市場を誘致するに足りるブロードバンド環境があることが一つの「必要条件」であることは分かるが、
「十分条件」は、日本が国として名護の国際金融センターを日本における唯一無二の国際金融市場としての優位性を持つことを、展望・実感・奨励することである。
しかし、現実は東京の二番煎じ、三番煎じ…否、十番煎じくらい
つまり、日本としては名護が要望するから、唯一ブロードバンド環境が整備されているという必要条件があるから、とりあえず計画を認め振興予算を付けたが…
本心は東京だけで十分だと思っているし、日本はオフショアの金融市場を持つことをほとんど奨励していないと言う意味では、その東京とて国際社会に対するアリバイ工作にすぎない…
それを物語るように名護の国際金融センターの実態は、オフショア市場の国際スタンダードには程遠く、そこに参入する企業の税金が時限的に軽減される程度のもので、そのインセンティブがなくなったときその後もそれらの金融機関が名護にいるという保障はない。
この図式こそが沖縄振興予算の大問題点…沖縄は思いつきで(そうでないものもあるがここでは論点を明確にするためにあえてそういう言い方をする)計画を立て、それを日本政府は言われるがまま許可し振興予算と題するお金を付けるが、計画を実行する必然性がもともとないためにそれらは結果的に頓挫し、振興予算は水の泡と消える、ということをあちこちでしかも何度も何度も繰り返してきたのである。
したがって、沖縄振興に係る予算は、日本政府も納得できる、沖縄も日本のウィンウィンの関係になれる、且つ沖縄が比較優位性、必然性を有する分野に傾斜的に投下されなければ、意味がない。
と、沖縄振興予算の問題点を断じておく…
次回は、南西航空復活に関して、そこに沖縄の比較優位性、必然性というインセンティブがあるのかどうかを考えてみたい。
※(1) タイミング論:日本が高度経済成長をしているころ沖縄は米軍統治下にあった。高度経済成長は単なる経済成長ではなく、敗戦からの復活の機運と国としての一体感、経済成長に係る国民全体及び個々人としてのスキルの習得、などその時期にしかない大きな副効果をもたらす。
※(2) 第二次世界大戦、GHQによる占領行政下にあった日本における経済復興のために実行された経済政策。当時の基幹産業である鉄鋼、石炭に資材・資金を超重点的に投入し、両部門相互の循環的拡大を促し、それを契機に産業全体の拡大を図るというものであった。工業復興のための基礎的素材である石炭と鉄鋼の増産に向かって、全ての経済政策を集中的に「傾斜」するという意味から名付けられた。
※(3) オフショア(Offshore)とは沖合を意味するが、原義を拡大して「海外」の意味に使うことがある。オフショア金融センターは、非居住者が資金調達・運用などの資金取引を自由に行える金融機関であり、タックス・ヘブンであることが多い。タックス・ヘヴン(Tax Haven)とは税金(Tax)からの避難地(Haven)の事であり、つまり全く税金が存在しないか、または極めて税率が低い国・地域を意味する。
第1章:沖縄振興予算の問題点
「沖縄経済の牽引役は観光産業である」と一口に言っても、県民生活の端々を見渡すとき沖縄経済は国からの沖縄振興予算なしに成り立たないというのが実態である。
沖縄復帰以後これまで総額8兆円もの振興予算がつぎ込まれた。
基地負担の問題や振興予算投下に係るタイミング論※(1)はあるにしても、県外の政治家全般、国家官僚のほとんど、県民以外の国民の多くは、口には出さないが「沖縄にどれだけお金をあげればいいんだ?これまで8兆円もあげたんだからもう十分だろう!これ以上はいい加減にしてくれないか!」みたいな感情をいだいているのではないだろうか!?
しかも、樋口氏が指摘するように、長引く構造不況、東日本大震災に端を発する復旧復興予算の確保、原発の補償問題、電力不足、それによる産業の停滞に起因する「日本にお金がない」という状況…
この現実を前にするとき、いくら日本国には沖縄に対する責任があると言えども、日本が「ない袖は振れない」状況にあるなら、我ら沖縄は単に「自立経済」を標榜するのではなく、本気で自立しなければならない。
それを考える上で沖縄振興予算の問題点を指摘しておく。
沖縄振興予算の問題点、と言うとき、「沖縄自立経済の確立」の名のもとに膨大な予算がつぎ込まれ、それは結果的にそのスローガンとは逆の「補助金漬け」という依存型経済社会を醸成してしまった、という事態が想起されるが、それについては「沖縄振興予算の病理」というフレームで認識しておいていただきたい。
ここで言う問題点とは、必要なところに、必要な金額が、必要なタイミングで、使われてこなかったということ、特に必要なところとは何かということに日本も沖縄も真剣に考えてこなかったということとする。
沖縄復帰当時、高度経済成長真っ盛りの日本にはお金があった…本来は沖縄振興、沖縄自立経済確立のために綿密なグランドデザインを描き、それをひとつひとつ実行すべきだった。
お金のあった日本はそれをぜず、権力と利権構造の枠組みの中で沖縄の言われるがままに沖縄振興という名目で予算を付けてきた。
しかし、総額8兆円もの振興予算がつぎ込みながら沖縄経済はいまだなお自立を果たせていないという状況…
くりかえすが、経済の自立発展のための要諦は、必要なところに、必要な予算を、必要なタイミングで、使うことである。
今で言うなら、選択と集中、現代史の用語に当てはめるなら「傾斜生産方式※(2)」であり、そこには選択すべき、傾斜生産すべき、対象の「比較優位性と必然性」がなければならないということである。
平成15年?名護市にできたオフショア※(3)の沖縄金融センターを例にとって話してみよう。
この計画自体の発想は悪くない…と思う。
日本政府が沖縄振興の一環で、都市圏と同等のブロードバンド環境を整備した。
この環境を一つの必要条件として、オフショアの国際金融市場を名護につくることを日本政府に認めさせ実現したものだが、僕の評価としてはうまくいっているとは言えない。
というのも、名護に国際金融市場をつくる比較優位性に乏しく、必然性を見いだせないからだ。
比較優位性や必然性を考える場合、必要条件と十分条件ががともに存在することが最も重要である。
沖縄に国際金融市場を誘致するに足りるブロードバンド環境があることが一つの「必要条件」であることは分かるが、
「十分条件」は、日本が国として名護の国際金融センターを日本における唯一無二の国際金融市場としての優位性を持つことを、展望・実感・奨励することである。
しかし、現実は東京の二番煎じ、三番煎じ…否、十番煎じくらい
つまり、日本としては名護が要望するから、唯一ブロードバンド環境が整備されているという必要条件があるから、とりあえず計画を認め振興予算を付けたが…
本心は東京だけで十分だと思っているし、日本はオフショアの金融市場を持つことをほとんど奨励していないと言う意味では、その東京とて国際社会に対するアリバイ工作にすぎない…
それを物語るように名護の国際金融センターの実態は、オフショア市場の国際スタンダードには程遠く、そこに参入する企業の税金が時限的に軽減される程度のもので、そのインセンティブがなくなったときその後もそれらの金融機関が名護にいるという保障はない。
この図式こそが沖縄振興予算の大問題点…沖縄は思いつきで(そうでないものもあるがここでは論点を明確にするためにあえてそういう言い方をする)計画を立て、それを日本政府は言われるがまま許可し振興予算と題するお金を付けるが、計画を実行する必然性がもともとないためにそれらは結果的に頓挫し、振興予算は水の泡と消える、ということをあちこちでしかも何度も何度も繰り返してきたのである。
したがって、沖縄振興に係る予算は、日本政府も納得できる、沖縄も日本のウィンウィンの関係になれる、且つ沖縄が比較優位性、必然性を有する分野に傾斜的に投下されなければ、意味がない。
と、沖縄振興予算の問題点を断じておく…
次回は、南西航空復活に関して、そこに沖縄の比較優位性、必然性というインセンティブがあるのかどうかを考えてみたい。
※(1) タイミング論:日本が高度経済成長をしているころ沖縄は米軍統治下にあった。高度経済成長は単なる経済成長ではなく、敗戦からの復活の機運と国としての一体感、経済成長に係る国民全体及び個々人としてのスキルの習得、などその時期にしかない大きな副効果をもたらす。
※(2) 第二次世界大戦、GHQによる占領行政下にあった日本における経済復興のために実行された経済政策。当時の基幹産業である鉄鋼、石炭に資材・資金を超重点的に投入し、両部門相互の循環的拡大を促し、それを契機に産業全体の拡大を図るというものであった。工業復興のための基礎的素材である石炭と鉄鋼の増産に向かって、全ての経済政策を集中的に「傾斜」するという意味から名付けられた。
※(3) オフショア(Offshore)とは沖合を意味するが、原義を拡大して「海外」の意味に使うことがある。オフショア金融センターは、非居住者が資金調達・運用などの資金取引を自由に行える金融機関であり、タックス・ヘブンであることが多い。タックス・ヘヴン(Tax Haven)とは税金(Tax)からの避難地(Haven)の事であり、つまり全く税金が存在しないか、または極めて税率が低い国・地域を意味する。
Posted by meza6 at 14:10│Comments(2)
│その他
この記事へのコメント
おはようございます
あの制服が な つ か し い ~ (笑)
(笑)




あの制服が な つ か し い ~
 (笑)
(笑)


Posted by ルミ at 2012年01月17日 06:56
>ルミ 様
ホント懐かしいですよね!(^^)!
でも、今はこういう写真が画像検索ですぐに探せる便利な時代になりました…
ホント懐かしいですよね!(^^)!
でも、今はこういう写真が画像検索ですぐに探せる便利な時代になりました…
Posted by meza6 at 2012年01月17日 09:04
at 2012年01月17日 09:04
 at 2012年01月17日 09:04
at 2012年01月17日 09:04